四半世紀のベスト①
いつの間にか26歳になり、人間五十年の時代ならば折り返し地点を過ぎてしまいました。
カート・コバーンやジム・モリソンに憧れて27歳になったらアメリカに行ってショットガン自殺しよう、なんて思い始めてから数年。あとタイムリミットまで一年ですが、もう強い希死念慮は失われて、ただ薄く引き伸ばされた生を生きていこう、と消極的な前傾姿勢を取りながら、なんとか息継ぎをしています。
これまでいろいろと本を読んできましたが、四半世紀のベストということで、影響を受けた本を記録しておこうと思います。基本一作家一作にしましたが、作者単位で影響を受けていることがほとんどです。
一言ずつ思い出語りもしながら、26年の省察をしていきたいです。
1、夢野久作『瓶詰の地獄』
はじめて彼の名前を知ったのは、高校時代。『ドグラ・マグラ』の読んだら発狂する、という惹句と米倉斎加年の妖しげな表紙にひかれて読み、チャカポコ、に戸惑い下巻で断念した。夢野久作の血と狂気の世界にどっぷり漬かると、向う側へといってしまいそうだった。『瓶詰の地獄』の表題作の冒涜的なせつなさ、何よりも「死後の恋」の森に吊るされた死体の描写が、決定的にぼくに「そういう」志向を植え付けたのだった。
2、大槻ケンヂ『ステーシーズ』
14、15、16の少女の死体が恋人を探して地上を彷徨う。友人に感化されて聞き出した「筋肉少女帯」のvo.大槻ケンヂによる小説。彼の世界観にもまた多大な影響を受けた。「機械」や「風車男ルリヲ」「香菜、頭をよくしてあげよう」のマッドなエモさがそこにはあった。はじめはなんてへたくそな小説だ、と思ったけれどいつの間にかずっと頭を占めているのは、死して恋する女の子たちとそれを再殺し、損壊させる部隊のことだった。
3、金井美恵子「兎」
はじめは小川洋子か高原英理のアンソロジーで読んだのだけれど、これには衝撃を受けた。『不思議の国のアリス』の変奏、残酷で血まみれの童話。庭で飼う兎を殺しては食べる父と娘が、やがて倒錯し、狂っていくさまが書かれている。ファンシーとゴシックが絶妙なバランスでミックスされた一品。この「兎」は単行本でもっておきたくて、大阪の商店街の古本屋で見つけて、すぐに買ったのだった。
4、赤江瀑『罪喰い』
『オイディプスの刃』が東西ミステリーベスト100にも選ばれているように、ミステリーの枠組みももっている赤江だけれど、その真骨頂は芸術の美に対する妄執と「魔」への心酔、匂い立つ官能だ。山尾悠子がベストに選ぶ「花夜叉殺し」は庭師に憑く庭とその主人の色物語という物語の中に、白黒映画のような翳と血と頽廃的な性がむんむんと漂っている。
鏡花はどれを選ぶか迷うけれど、手毬唄の旋律と球体のイメージが全体を貫く、屋敷の怨念の物語にした。彼の文章は聞いたことのない日本語がたくさんでてくる。その絢爛な漢字と翻訳不可能な比喩を目で追っているだけでも楽しい。純粋な言葉の世界。「外科室」「春昼」「夜叉が池」「天守物語」「高野聖」「義血侠血」どれも絶品だ。繊細のある種の極致ともいえる文章。畠芋之助の別名もあるけれど、鏡花でよかった。
6、キャリントン『耳ラッパ』

- 作者: レオノーラキャリントン,Leonora Carrington,野中雅代
- 出版社/メーカー: 工作舎
- 発売日: 2003/07
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
エルンストの恋でレメディオス・バロの友人のシュルレアリスト画家レオノーラ・キャリントン。魔術だとか錬金術だとか神話だとか、そういった妖しげなものが好きなぼくは、いつの間にかシュルレアリズム絵画にも惹かれていった。耳ラッパは、92歳の老女が友人のカルメラから耳ラッパという補聴器のようなものをもらうところから物語が始まる。そうして老女の冒険は、世界の終末というところまで進んでいく。

- 作者: アンドレブルトン,Andre Breton,巖谷國士
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 1992/06/16
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 47回
- この商品を含むブログ (52件) を見る
高校の時に知ったマグリット以来ダリ、エルンスト、キリコ、ムンク、モロー、ルドン、ベーコンなど、絵は風景画よりもどこか不穏なものが好きだった。ブルトンの「シュルレアリスム宣言」では、理性の箍を取り払い、夢や無意識の想像力を発現させることが述べられている。剥きだしのイメージの奔流は、例えば麻薬や自動筆記や子供の精神への逆行によって得られる。のちのちの志向を生むことになる諸作の生みの親だ。
8、山尾悠子『夢の遠近法』
日本の作家では一番か二番に好き。彼女の純粋に言葉のみで作り上げられた世界には、ある種の取っつきづらさはあるけれど、一度その砦に立ち入ったらもう帰っては来られない。下半身が異様に発達した踊り子、夢を語る獏、囚われの侏儒、太陽や月が中央を通る無限の塔。澁澤龍彦の影響下にありつつ、独自のイメージの世界を作り上げる彼女の新作を今も読み続けられるというのは、大きな喜びだ。
9、ボルヘス『伝奇集』
ぼくの周囲ではよくボルヘスの名前が挙がっていた。ミステリー、SF、ポストモダン、幻想と違った趣味をもつ4人が共通に話題にするのはボルヘスだった。書物の世界の住人、ボルヘス。「トレーン、ウクバール」「バベルの図書館」など奇想天外な短編は、短いながらそこに収められた世界は長編もかくや、だ。円環と無限を主題にすえた諸作はマルケスと一緒になって文学を変えてしまった。がつん、とくる一冊である。
10、残雪「暗夜」

暗夜/戦争の悲しみ (池澤夏樹=個人編集 世界文学全集 1-6)
- 作者: バオ・ニン,残雪,近藤直子,井川一久
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 2008/08/09
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 79回
- この商品を含むブログ (28件) を見る
中国版ボルヘスといってもよいような残雪の薄暗く大きな絶望に裏打ちされた作品群。文化大革命の影響をうけた彼女には外部とのわかりあえなさ、という暗澹たる気持ちが常に存在している。「朝」か「夜」なら明らかに「夜」に属する、そんな作品だ。永遠に明けない夜の主題は繰り返し登場する。この『世界文学全集』の読書会を隔月でしているけれど、毎回強い刺激を受ける作品ばかりだ。
11、ルネ・ドーマル『類推の山』

- 作者: ルネドーマル,Ren´e Daumal,巌谷国士
- 出版社/メーカー: 河出書房新社
- 発売日: 1996/07
- メディア: 文庫
- 購入: 6人 クリック: 27回
- この商品を含むブログ (29件) を見る
ドーマルはシュルレアリスムの周辺の作家ではあるけれど、彼らの無機質な感じとは違って、この小説は表向き冒険小説である。世界のどこかにある「類推の山」への登頂を夢見る男女の小説だ。けれど、そこにはいくつもの魔術的イメージがちりばめられている。未完ゆえに無限に開かれていて、圧倒的な想像力が喚起され、なぜか元気の出てくる一冊。いわゆるファンタジー小説のようで、読みやすいのもよい。
12、結城聖『テイルズオブシンフォニア』
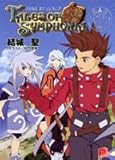
テイルズ オブ シンフォニア シルヴァラント編 (集英社スーパーダッシュ文庫)
- 作者: 結城聖,松竹徳幸
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 2003/11
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (5件) を見る
ぼくが小説を書き始めたのも、魔術的なものに興味を持ち始めたのも、音楽を聞き始めたのも、オタクになったのも、すべて中学でであったナムコのRPG「テイルズオブシンフォニア」のせいだった。さかのぼって「ファンタジア」から「ベルセリア」にいたる巨大な世界観によってぼくの90%くらいは構成されていると思う。これのせいで人生が狂ったのは間違いない。
13、二階堂奥歯『八本脚の蝶』
おどろおどろしい本でおなじみの国書刊行会の編集者にして、25歳で自殺した、「生きてきた日数よりも読んだ本の方が多い」博覧強記の女性。もう二階堂奥歯よりも長く生きているということが信じられない。彼女の日記である『八本脚の蝶』には、日々のよしなしごとから、ブランド、読んだ本などが雑多に書かれているけれど、その趣味の広さと造詣の深さに恋してしまう。もうこの世にはいないのだけれど。
宮沢賢治のように色をもった言葉でつづられる童話。人間がいなくなった夜の学校には、星や月を天に縫い付ける天使たちが集まる。そこに迷い込んだアリスの一日だけの幻。これが文藝新人賞をとっているのは、とてもすごいこと。この小説を読むと、いつでもひとりの女の子がぼくの頭に浮かぶ。長野まゆみや寺山修司が好きで、ぼくに『旅のラゴス』をくれた女の子。結局ぼくは何も伝えられず、彼女はまさに幻のように消失してしまった。
15、小川洋子『寡黙な死骸 みだらな弔い』
はじめて読んだのは『博士の愛した数式』だった。それからしばらくして、この本に出会い、そして彼女の描く硬質な世界の虜になった。形あるものの中に蠢くぐじゅぐじゅしたもの、人間の湛えるグロテスクな内面が、11編の連作短編で描かれる。「果汁」は昔、国語のテストか何かで読んで、以来ずっと心に残っていた短編。再会したのは偶然で、こうした奇跡的な体験が積み重なるにつれて、いっそう読書にのめり込むのだった。
16、川上弘美『蛇を踏む』
小川洋子の紹介で手に取った、おそらく初めて読んだ芥川賞受賞作。蛇を踏んだら女になった、という童話のような話で、なるほどこれが文学というやつかという先入観が刷り込まれることになった。それ以来ぼくにとって文学とは、この世のことでないような不思議な作品をさすような言葉になった。2000年以降の芥川賞受賞作をずっと読んできたけれど、忘れられない一冊だ。
夏目漱石もまた一冊選ぶのが不可能な作家だ。『三四郎』『それから』『門』の重層的なエモ、『草枕』の言語芸術、『坊ちゃん』『彼岸過迄』のエンタメ、『こころ』の内省や衝撃、どれも一級なのだけれど、やはり初めに読んだ「第一夜」の圧倒的な美しさが心に残る。たった4ページなのに、もう心がわけのわからないくらい動く。「百年はもう来ていたんだな」という言葉がしみる。
18、島尾敏雄「夢屑」
こちらも夢を描いた島尾敏雄の短編。夏目漱石や、内田百閒の『冥途』、タブッキの『夢のなかの夢』など夢を題材にした作品は多いけれど、島尾の夢は暴力的で、時には死の香りも漂う。『死の棘』で書かれる現実の不安が、夢の中に投影されているのだろうか。夢はうつつ、うつつは夢。胡蝶の夢だ。第三の新人に分類される作家だけれど、こじんまりしたよさというのを超えた何かを感じる。

百年の孤独 (Obra de Garc´ia M´arquez)
- 作者: ガブリエルガルシア=マルケス,Gabriel Garc´ia M´arquez,鼓直
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2006/12
- メディア: 単行本
- 購入: 25人 クリック: 269回
- この商品を含むブログ (278件) を見る
かなり多くの人が文庫化したら、と思っているであろうラテンアメリカ文学の旗手マルケスの傑作。『エレンディラ』などで書かれたマジックリアリズムが各所に散りばめられた、アウレリャノの血と、マコンドという土地の物語。人が死ねば黄色い花が降り、恋した人間を死に至らしめる少女は突如昇天し、死んだはずのジプシーは繰り返し蘇る。読み終わった後には深いため息が自然と漏れた。
日本における土地と血の物語。ぼくは一時期熊野に入れ込んでいて、三山はもちろん伊勢にいたるまでの生と死の蠢く妖しげな土地へ旅に出てみた。鬱蒼とした森、海の静寂、自然のダイナミズムを感じた。そこに育った中上は、路地を舞台に「秋幸」の関係自体を物語にする。異父、近親相姦、暴力、濃密な熱量が文章から漂ってくる。ここまでの汗を描いた小説を、ぼくは知らない。
谷崎潤一郎の短編集を作ってください。もしこんな仕事がきたらぼくは断る。それは不可能だからだ。はっきりいって谷崎の短編はどれも珠玉だ。だからぼくは谷崎の中でも特に気持ち悪いこの作品をあげておきたい。女優の妻をもつ映画監督のもとに奇妙な男が現れる。「あなたは奥さんの撮り方がわかっていない、うちにきなさい」。訪れた男の家で、監督が見たものとは。谷崎は気持ち悪い、そこがいいのだ。
何度も自殺を試み、常にヘロインを傍らに生活したカヴァンの短編集。彼女の短編はとにかく不穏だ。よく天井を見て一日を過ごすことがあるのだけれど、ずっとあの白色を見ていると、なんだか禍々しいうねりが見えてくることがある。そういう精神の一瞬の動きを、彼女は文章に落としている。『氷』もながらく絶版だったけれど、文庫になってずいぶん手に入りやすくなった。
23、ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』
ぼくの高校では、毎回英語の定期考査後に英書が配られ、次の考査までの課題となっていた。そこではディックやクラークなどのSF、コリンズやキングなどのミステリー、シェークスピアやディケンズなどの古典、そしてこの『ドリアン・グレイの肖像』が取り扱われた。当時1年生だったぼくは、同性愛、自己陶酔、ピュグマリオンコンプレックスという奇怪な物語に打ちのめされたのだった。これを高1で読ませるのはどうかしている。そのあと『サロメ』で第二の衝撃を受けるのだった。
向精神薬を飲みすぎて夜しか動けなくなる、図書館のほうが居心地がよい、気分が落ち込んだときは歌をうたう。尾崎翠の描く精神衰弱者には、ただひたすらわかる、わかると頷くばかりだ。少女漫画風の筆致の中に、思わず笑ってしまうような会話があり、恋愛があり、けれど全体的にどこかずれている。このずれ具合がやわらかい文章にのって他にない味を出している。
25、カフカ『変身』

- 作者: フランツ・カフカ,Franz Kafka,高橋義孝
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1952/07/28
- メディア: 文庫
- 購入: 18人 クリック: 359回
- この商品を含むブログ (359件) を見る
これも高1の時、憧れていた国語の先生が教えてくれたのがカフカだった。親が働く本屋へ行って買った。薄いその小説を朝、学校へ行く前に読んだ。「なんだこれ」と思った。朝起きたら虫になっていた、妹や親にはわかってもらえない。読み終わって、笑いやらかなしいやら、いろいろな感情が虫の足のように蠢いた。そう思って振り返れば、ミステリーや人間ドラマよりも早く、ぼくはワイルドやカフカの妖しい世界に巻き込まれていたのだった。
その②はこちら

















